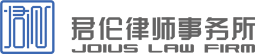2025年7月23日、最高人民法院は「執行異議の訴えの審理における法律の適用に関する解釈」(以下、「本解釈」という)(2024年12月14日最高人民法院裁判委員会第1938回会議で採択、2025年7月24日から施行されている.)を公布した。 本解釈は全23条で、執行異議の訴えに関する管轄、当事者の訴訟地位、他の訴訟手続きとの連携、特殊な主体の権益保護、虚偽訴訟の懲戒などについて全面的かつ詳細な規定が設けられる。現行の法律体系において、民事訴訟関連の裁判規定と整合性を保ちつつ、執行異議の訴えにおける諸規定と手続きの連携を細分化し、実際の訴訟における実効性を高め、訴訟資源の無駄を避けるとともに、執行異議の訴えにおける関係当事者の適法な権益を守る要請に対して応えたものである。本稿では、「本解釈」の5つの核心的なポイントにあたって解説する。 ポイント1:管轄規定を細かくすることで—紛争解消と効率化に取り組み 本解釈は、まず執行異議の訴えにおける管轄の問題を解決する。第一条では、執行対象物の所在地を管轄裁判所を選択する基準とすると明確に定める。これは、実践で複数の裁判所による重複の差し押さえでもたらす管轄衝突の問題に直面し、明確かつ唯一の管轄の連結点を確立することで、手続き上の混乱が源から減少させる。第二条では、輪候差し押さえ(順番待ち執行)の状況で当事者の訴訟上の地位を革新的に規定する。これは、最初に差し押さえを行った者または優先権を有する申請執行者を被告とし、その他の輪候主体を第三者とする。この設計は、すべての利害関係者を一度に訴訟手続きに取り込み、情報の透明性と紛争の実質的解決を大幅に促進し、多重訴訟により当事者の負担を軽減し,訴えの負担を著しく軽減している。さらに、第四条および第五条では、異議の訴えにおいて執行対象の権利確認請求と給付請求を併せて審理できることを明記している。これにより、訴訟資源の配分を最適化し、司法効率を向上させられる。 ポイント2:手続き連携メカニズムのシステム化—効率と救済のバランス 執行のプロセスと異議の訴えのプロセスの間で生じやすい衝突と矛盾に対し、本解釈はよりシステム化な解決策を構築する。第六条では、執行裁判所が執行を継続する決定を下した場合、案外人(第三者)が権利の救済を求める具体的なルートが定められ、執行の推進により権益を保護する可能性を失われることを避ける。第十条では、案外人の異議申請が却下された後、申請執行者の利益をきちんと保護するやり方を規定し、異議手続きで執行の過度な遅延を防止している。この双方向の保護制度は、執行効率と当事者の適法な権益の保護の関係を適切に調整し、取引の安全と安定を維持できる。特に注目すべきなのは第七条から第九条に、「執行の根拠となる法律文書が廃止されまたは変更された場合(基礎の消失)」、「原判決・裁定が再審による変更された場合」、および「被執行者が破産プロセスに入った場合」という三つの特殊かつ複雑な状況に対して、初めて明確な審理規定を制定する。この条項は、裁判所がこのようなプロセス上の難題に直面する場合に、審理を中止するかまたは継続するかという判断の基準を提供し、司法実務の問題点に対応できる。 ポイント3:特殊主体の権益保護の深化—国民の生計を重視 本解釈は、国民の生活や生計に関連する特殊主体の権益を優先的に保護する姿勢の現れであり、詳細な規定が設けられる。第十一条および第十二条では、条件に合う商品住宅消費者(購入者)に強制執行を排除する法的権利を明確に与え、所有権移転登記の請求または賠償の取得を認めることで、基本的な居住権益を強力に保障できる。第二十条では、適格な賃借人が法定条件に満たす場合に執行を排除する権利を有することを確認し、賃貸関係の安定を維持できる。第十八条では、不動産徴収と補償にあたって、被徴収者が特定の条件で工事代金の優先権、抵当権などの商業債権に対抗できる規定を確立し、弱者層の権益保護を重視する姿勢の現れである。第三条では、権利が確認された後の執行解除の実践的なルートを設定し、「権利認定→執行排除→執行解除」という全体的な循環を形成し、保護を実現できる。 ポイント4:不動産買受人の執行排除規定の体系化 本解釈は、複数の条項(第十三条から第十六条および第十九条)を通じて、不動産買受人の強制執行を排除する条件とルートがこれまでにない細分化と体系化される。これらの条項では、全額で払い済み、占有中、自己責任ではない理由で所有権移転登記が未完了など、異なる状況で不動産買受人が強制執行を排除する具体的な要件と審査の基準を詳細に定める。第十七条では、不動産を工事代金の抵当とする場合において、特定の条件に合う買受人の権利が抵当権や一般債権に優先して、執行を排除する保護を受けられることを特別に定める。このような一連の規定は、不動産取引に関する執行異議の訴えにおいて、統一的で明確かつ予測可能な裁判基準を提供し、規定の実効性と裁判結果の安定性を大幅に高める。 ポイント5:虚偽訴訟の処罰の厳正化—立体的な責任体系の構築 執行異議の訴えにて生じ得る虚偽訴訟に対し、本解釈第二十一条は厳正かつ全面的な責任追及の体制を構築する。本条では、案外人、被執行者、申請執行者のいずれでも、虚偽訴訟が成立した場合、敗訴などの民事責任を負うだけでなく、判決・裁定拒否罪などの刑事責任も追及されると明確に規定する。さらに厳しいのは、責任追及の範囲が虚偽訴訟に参加した代理人、証人、鑑定人などの関連主体までにも広がっている。この規定は、虚偽訴訟の取り締まりを抽象的な政策から、拘束力と実効性を備えた具体的なルールと転換させ、事後の厳罰の仕組みを踏まえ、権利濫用を効果的に防止し、訴訟環境を浄化し、司法の権威と信用体制が維持できる。 本解釈は、4つの角度からの制度革新——「管轄規定による効率高め」、「手続き連携による紛争解決」、「権益のレベル化による争いの処理」と「懲戒制度による訴訟濫用の防止」を通じて、執行異議の訴えが「プロセスが形骸化している」から「実質的に紛争を解決すること」へ転換し、「効率と公正の両立」を図る執行異議の治理体系の構築に重要な支えを提供する。これらの取り組みは、執行異議の訴え制度を「規定あり」から「規定が良い」へと進化させ、案外人の適法な権益をより良く守り、司法の公正を維持できる。